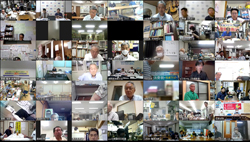補助金獲得 経営伸ばす思い伝え 大商連相談員養成講座開く

大阪商工団体連合会(大商連)は先ごろ、補助金獲得・相談員養成講座「実践編」を開催し、33民主商工会(民商)の90人が参加しました。
大商連の経営自治体部長で阿倍野民商の中村大思さん=卸・小売り、布施民商の小田利広事務局員と山下孝明さん=美容室=が報告しました。
中村さんは、持続化補助金を活用し、フランチャイズをやめて、独自ブランドを立ち上げた民商会員のラーメン店の事例を紹介。「パソコンは使えなかったが、商売への思いや、メニューのこだわりがしっかりあったので、それを一緒に分かりやすくまとめ直して、採択につなげた。補助金は、あくまで経営を伸ばすための一つの方法。まずは、どうやって経営を伸ばすかを文章にすることが大切」と強調しました。
小田さんは、持続化補助金を使ってレーザー溶接機を導入し、取引先の確保につなげた溶接業の民商会員の事例を報告。「事業計画は簡潔・明瞭・論理的な文章を意識し、図表も使って、素人でも分かるよう工夫することが重要」と話しました。
大阪府のテイクオフ補助金を使ってオートシャンプーを導入した山下さんは、パソコン申請の苦労や採択後の注意点などを説明。「一人で対応するのは大変。相談できる民商は心強い」と語りました。
大商連は、「商売を維持・発展させるため、まずは挑戦しよう。何度か申請すれば、採択率も上がってくる。みんなで励まし合って、頑張ろう」と呼び掛けています。
国保料減免 総額約17万円減額も 大阪・守口民商 集団減免申請の「成果」
「国民健康保険(国保)料が下がって助かった」―。大阪・守口民主商工会(民商)は30年以上、毎年、国保料の集団減免申請と守口市への要請に取り組んでいます。今年は7月上旬に、81人が申請(うち却下は1件)し、減免された会員に喜びの声が広がっています。
大阪府は今年4月に、府内の国保料を「完全統一」しました。守口市はこれに先駆けて2018年度から、府が提示した統一保険料を丸のみ。周辺の各市が医療分の料率を独自に低く設定し、市民負担の軽減を図っていた際にも、”府言いなり”の高い国保料水準を維持してきました。さらに、減免基準も変化。以前は、所得減だけでなく、医療費負担や借金の返済など、さまざまな理由で減免でき、所得減少の最低基準や減免の端数切り捨てなども無かったものが、18年度には完全統一化基準の「30%以上の所得減でないと、減免できない」「納期限を過ぎた保険料は減免しない」などに改悪されていました。
それでも、長年の運動の結果で勝ち取った「出したら、すぐ減免」などの成果は、完全統一化された今年度も、市は「これまでと用紙も、やり方も変わらない」としています。
今年初めて減免申請を行い、総額約17万円の減額が認められたN・Tさん=塗装工事=は「昨年、取引先の都合で、仕事の9割方が無くなりました。国保も下がると思っていたのに、夫と私の2人分で月に4万円近い請求が来てびっくりした」と語ります。
民商に相談し、早速、減免を申請。国保料は月2万2千円に減額されました。「こんなに下がるんやと、今度もびっくり。食料品も、塗装用の資材も何でも高くなっている今、めっちゃ助かります」
燃油高補助 民商だから申請できた 大阪・泉佐野民商 K・Mさん=飲食
「民商が無かったら、『分からん!』って諦めてたところや。軽自動車1台分で1万円の支援金やけど、ありがたいわ」―。大阪・泉佐野民主商工会(民商)のK・Mさん=飲食=は、泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金の手続きを済ませて一安心しています。「コロナ禍に入会して、給付金など、いろいろな手続きの相談に乗ってもらった。病気になった時も共済金で助かったわ。民商に入って、本当に良かった」と、とても喜んでいます。
この支援金は、泉佐野市に事業所を持つ事業者の車両ごとに支援金を給付する市の独自制度です。昨年に続き設けられ、事業用の車両なら、何台でも申請可能です。
支援金制度を知らせる民商ニュースを見て、複数の会員から相談が寄せられています。泉佐野民商では、申請期限となる9月末まで声掛けを広げ、燃料や物価の高騰に苦しむ会員の商売を少しでも応援しようと話し合っています。
泉佐野市 原油価格高騰対策事業者支援金
原油価格高騰の影響を受ける、泉佐野市内の事業者の経営再建および事業継続を支援するために給付される支援金。
●対象
自動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市内で登録をされている自動車で、給付対象者が事業用に使っている車両
※個人事業主で、自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であり、かつ「用途」が「乗用」の場合、1台まで。その他は台数制限無し
●給付額
大型自動車および大型特殊
自動車…5万円
中型自動車および準中型自動車…3万円
普通自動車…2万円
軽自動車…1万円
●申請期間
8月1日~9月30日まで

 03-3987-4391
03-3987-4391